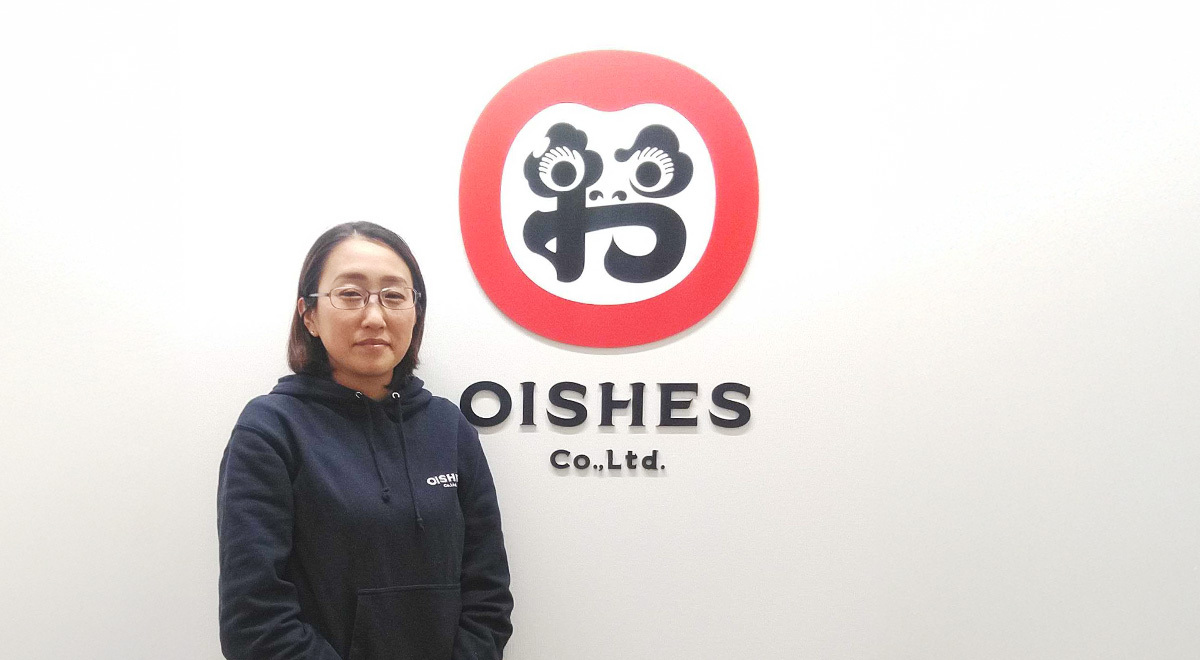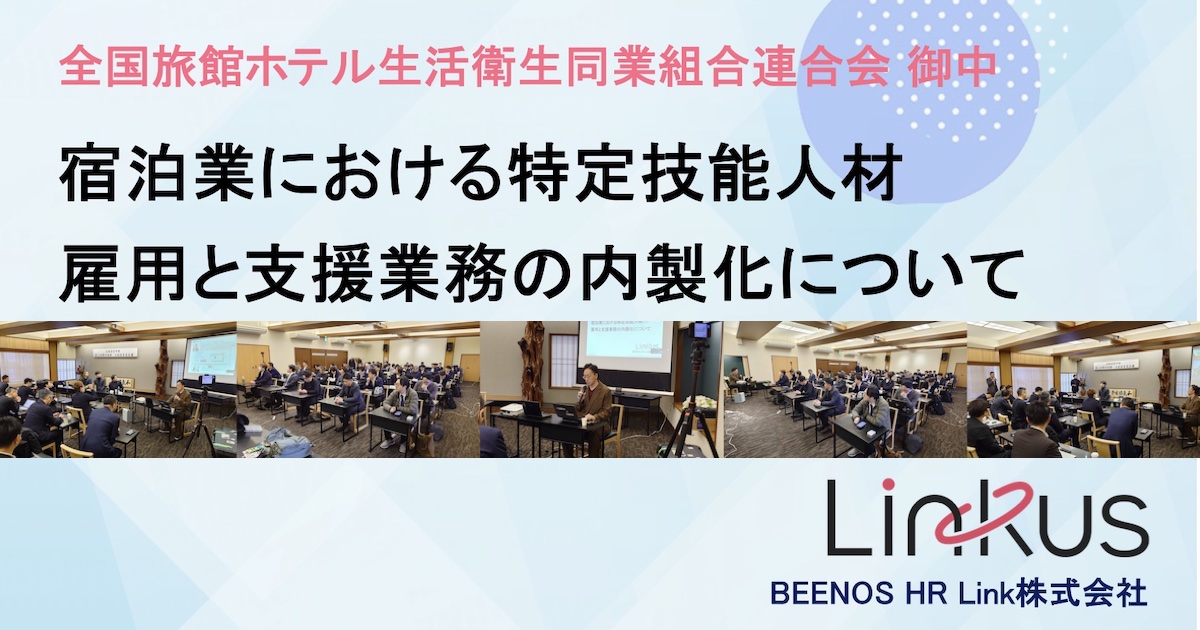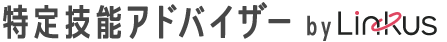株式会社麺食は「喜多方ラーメン坂内」をはじめ、国内外で多角的な飲食店経営を展開する企業です。同社は、制度ができる前から外国人雇用に積極的に取り組んでおり、現在は特定技能外国人を多数雇用しています。
今回は、株式会社麺食の執行役員を務める藤原栄朋氏に、外国人雇用を始めたきっかけや、同社の支援ノウハウ、今後の展望について伺いました。
外国人雇用は「日本の未来」。20年前から始めた人材活用の取り組み

── 本日はお忙しいところ、ありがとうございます。まずは、御社の事業内容について教えていただけますでしょうか。
「麺食(めんしょく)」は1988年に創業し、今年で38年目を迎える会社です。
現在は「喜多方ラーメン坂内」を主軸に、国内に69店舗、アメリカに9店舗、ドイツに1店舗を展開しています。ラーメン事業以外にも、アジア料理や日本そば、スペインバル、さらには海外で日本料理やカレー店も運営しており、多角的に事業を展開しています。
── ありがとうございます。特定技能に限らず、外国人雇用を始めたきっかけや背景を教えていただけますでしょうか?
特定技能制度が始まる前から外国人雇用には取り組んでおり、もう20年ほどになります。
きっかけは、現社長である中原 誠の経験です。彼が当社に入社する前、お台場にある飲食店で店長をしていました。お台場は交通の便の悪さもあり、時給を上げても日本人がなかなか集まらない場所だったんですね。そんな中、厨房にはミャンマー人やバングラデシュ人など、多くの外国籍スタッフが働いており、彼らが非常に優秀でした。
中原は、この光景こそが「日本の未来」だと感じ、今から外国人雇用を始めなければ人手不足に陥ると考えたそうです。その後、当社が運営する「喜多方ラーメン坂内」に当時一緒に働いていたバングラデシュ人のスタッフを迎え入れたのが始まりです。この方は現在、当社の直営店で店長を務めています。
この方の採用は、外国籍人材だから、安価な労働力ということではなく、もともと一緒に働いていたことから人となりや能力の高さも把握しており、日本人を採用するのと同様に一緒に働いてほしいということからの採用でした。
──外国籍人材の雇用を開始した当初から、そうした信念を持って雇用されていたのですね。
はい。2019年に特定技能制度ができたことで、外国籍人材を雇用する企業や雇用を考えている企業からの相談を受けることが増え、現在では「喜多方ラーメン坂内」の加盟店様や飲食業界を対象に、当社の知見を活かした登録支援機関としての活動も行っています。
支援の強みは「当事者」であること。おせっかいな「近所のおじちゃん」として寄り添う

── 支援業務を行う上で、御社ならではの強みや工夫されていることは何でしょうか?
当社の強みは、なんと言っても私たちも外国籍人材を雇用している「当事者」であることです。
一般的な登録支援機関は、法律で定められた3か月に1回面談を実施します。しかし、私たちはそれだけでは不十分だと感じています。3か月に1回の面談では、本当の悩みやトラブルを把握しきれません。そのため、私たちは3か月に2~3回は面談を行うなど、積極的にコミュニケーションを取るように心がけています。
また、当社の外国籍社員には、ベトナムやミャンマー、中国、バングラデシュ、インドネシアなど、さまざまな国籍の社員が在籍しています。面談の際には、単に通訳を介するだけでなく、同じ国籍の社員が「日本の先輩」として相談に乗ったり、アドバイスをしたりします。
また、そうした相談を受ける当社の社員には、相手に対して、日本の先輩としてお手本になってほしいということも伝えています。
私たちは、あくまで雇用企業様と特定技能外国人の間に入ってサポートする「おせっかいな近所のおじちゃん」のような存在だと思っています。
雇用契約を結んでいる親子の関係には立ち入らず、両者が円滑にコミュニケーションを取れるようサポートする。例えば、外国人材が困ったときに、直接雇用企業に言いにくいことを私たちが聞いて、うまく伝えます。逆に、雇用企業が外国人材に伝えたいことをうまく伝えられない時に、私たちがサポートする。このような立ち位置を大切にしています。
「安価な労働力」と考える企業はNG。長く日本で働いてもらうための独自のノウハウ

── 外国人材を雇用する上で、特に工夫されていることはありますか?
当社は採用の際、必ず現地にいって面談を行うようにしています。オンラインでの面接などもできますが、その人の人となりを把握したうえで雇用したいからです。
日本語の能力が高いからといって、必ずしも業務に適正があるわけではないので、その方の能力や人柄を見るようにしています。
また、現地の送り出し機関と密に連携し、日本語教育はもちろんのこと、日本の生活習慣や文化的な理解を深めるための教育にも力を入れています。
── 特定技能人材のキャリアパスについては、どのように考えていますか?
当社では、特定技能人材を日本人と全く区別していません。キャリアパスにおいても、同様です。
直営店23店舗のうち、3分の1の店長が外国籍です。彼らが日本人スタッフをマネジメントする光景は、当社ではごく当たり前のことになっています。
もちろん、特定技能1号の5年という期間を終えてからも長く日本で働いてもらえるよう、特定技能2号への移行支援は積極的に行っています。
── 貴社では、BEENOS HR Linkが提供する支援業務管理ツール「Linkus」を導入してくださっています。導入の決め手は何でしたか?
「Linkus」を知ったのは、ネット検索でした。最終的な決め手は2つあります。
1つ目は、送り出し機関や受け入れ企業と情報をやり取りする仕組みが、非常に便利だと感じたことです。これまでExcelで管理していた膨大な情報を一元管理できるようになり、効率化が図れると思いました。
2つ目は、プロダクトに対する御社の姿勢です。岡崎社長が、日々、プロダクトの改善に取り組んでいると知り、私たちと同じように「成長していきたい」という思いを感じました。今後も、当社の悩みを共有しながら、共に成長していけるパートナーになっていただけると期待しています。
── Linkusを導入されて、特に役に立っている機能や、業務効率化につながった点はありますか?
自社の従業員だけではなく、登録支援機関としても活動するようになったことから、Excel等の管理だけでは対応が難しくなったこともあり、Linkusを導入しました。業務工数の削減という点では、非常に役立っています。一方で、Linkusの性能をまだ十分に生かし切れていないんじゃないかとも思っていて、実際に真価を発揮するのは送り出し機関との連携部分だと思うんです。今後、送り出し機関がデータを入力してくれるようになったりなどできれば、さらに活用していけるのではと思っています。
── 特定技能外国人の受け入れを検討している企業へ、何かアドバイスはありますか?
弊社では、「安価な労働力が欲しい」といった、都合の良い労働力を求める企業とは、残念ながらお付き合いしないようにしています。そのような考えでは、外国人材も長く続かず、必ずトラブルになるからです。
日本人と外国人を区別しないこと。そして、雇用契約の基本は「お金」にあることを忘れないことです。日本人は「会社が好き」「仕事が好き」といった感情的な部分で長く勤めてくれることがありますが、外国籍の方々は、やはり生活がかかっていますので、お金に関する話はストレートに聞いてきます。ただ、日本人もはっきりとは言わないだけで、根本の部分では共通していると思います。そこで「結局、お金か」とネガティブに捉えるのではなく、率直に伝えてくれる彼らと、対等に向き合うことが大切だと思います。