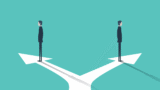2024年3月の閣議決定で、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加された在留資格[特定技能]。人手不足が深刻化する日本で、新たな労働力・即戦力としてますます注目されています。
この記事では、特定技能の「1号」と「2号」の違い、取得条件、対象職種などを詳しく解説。受け入れる企業が満たすべき条件や義務も解説しますので、こちらもご参照ください。なお、特定技能の採用・雇用は特定技能特化型のプラットフォーム[Linkus]がお手伝いいたします。自社支援・内製化については[特定技能アドバイザー]にご相談ください。


在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、日本に合法的に滞在できる資格(在留資格)のひとつ。特定技能の資格を持つ外国人は日本国内での現場労働が認められています。この在留資格[特定技能]は、中小企業・個人事業主を中心に広がる人材不足の課題を解決するために創設されました。人手不足が深刻化している職種について、一定の専門技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、というのが特定技能創設の趣旨です。
したがって、「外国人に技能を習得してもらう」という目的を持つ技能実習とは根本的に制度の趣旨が異なります。要件だけでなく支援に関する登録支援機関や監理団体についてなど、詳しい違いについてはこちらの記事をご覧ください。
特定技能1号と2号
特定技能には1号2号の2種類があります。この章では、それぞれの在留期間や技能水準などを解説します。
特定技能1号とは
特定技能1号とは、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格です。簡単に言うと、ある程度実務経験を積むことでこなせるようになる業務を行う外国人が対象となります。
特定技能1号を取得するには、後述する「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアする必要があります。在留期間は最大5年までとなっており、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新が必要です。受け入れる企業や登録支援機関などのサポートを受けられるものの、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号とは
特定技能2号とは、「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格です。要するに、特定技能1号よりもレベルの高い技能を用いる外国人が対象です。
特定技能2号を取得するには、業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。(一部の業種では日本語検定も必要。)受け入れる企業や登録支援機関などのサポートは対象外となるものの、条件を満たせば配偶者と子供の帯同が認められます。また、3年、1年または6か月ごとの更新を行えば、無期限で日本に滞在し続けることが可能で、永住許可の条件である在留期限に算入もされます。
特定技能の対象職種が拡大!
これまで12分野だった特定技能ですが、2024年3月に4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)の追加が決定しました。(新しい4分野に関しては2025年に受け入れが開始される見込みです。)
特定技能1号を取得できる特定産業分野
在留資格 特定技能1号 を取得できる特定産業分野は『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針』に明記されています。この基本方針では、具体的に下記16種類の分野で特定技能を取得できるとしています。
[table id=9 /]
分野ごとに詳細な職種が指定されています。たとえば[造船・舶用工業]だと、溶接 や仕上げ、塗装などと細かく職種が定められています。詳しい内容については、こちらの記事をご参考にしてみてください。
特定技能2号を取得できる特定産業分野は11種類
2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
介護と新たに追加された4分野を除く11種類が特定技能2号の対象となり、5年の上限を超えても働き続けることが可能になりました。
特定技能1号の取得条件
特定技能1号の在留資格を取得するための条件は①「技能試験と日本語能力試験に合格すること」、または②「技能実習2号を修了すること」。ここでは具体的な内容について解説します。
条件①:技能試験と日本語能力試験に合格すること
特定技能を取得する条件のひとつは、技能試験と日本語能力試験に合格することです。どちらの試験も、外国人が住んでいる現地国にて実施されます。(日本語基礎テスト以外は、日本国内でも実施されています。)
◆技能試験:
分野ごとに必要となる技能の知識を問う試験。例えば建設業の場合、国交省が定めた建設分野特定技能評価試験への合格が必要。試験の範囲は分野によって異なるものの、基本的には学科試験と実技試験の双方が科される。
◆日本語能力試験:
日本で在住・就労するのに必要となる最低限の日本語力を示す試験。具体的には「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格が求められる。ただし介護分野では上記の試験に加えて介護日本語評価試験の合格も必要。
条件②:技能実習2号を修了すること
技能実習2号とは、在留資格[技能実習]のうち2・3年目の活動を行う外国人に与えられるものです。技能実習2号を良好に修了した外国人であれば、試験を経ずに特定技能の在留資格を取得できます。
「良好に修了」とは「技能実習から特定技能へ移行」もしくは「技能実習を終えて一旦帰国したが特定技能としてまた日本で働きたい」場合、技能検定3級などに合格している、または評価調書を提出できることです。
特定技能所属機関
特定技能所属機関とは、特定技能を持つ外国人を雇用する企業のことです。この章では、特定技能所属機関が外国人を雇用する条件や、守るべき義務について解説します。
特定技能所属機関が外国人を受け入れる条件
外国人を受け入れるには、4つの条件をクリアする必要があります。
条件1:外国人との雇用契約が適切な内容であること(報酬額が日本人と同じかそれ以上)
条件2:5年以内に出入国や労働に関する法令に違反した事実がないこと
条件3:外国人労働者を支援する体制が整備されていること(例:外国人が理解できる言語で支援する体制など)
条件4:外国人を支援する計画が適切であること(計画には生活に必要な日本語習得支援や入国前の生活ガイダンスの提供、在留中の生活オリエンテーションの実施、などを行う旨を明記)
特定技能所属機関の義務
特定技能所属機関として外国人労働者を受け入れるには、3つの義務を果たさなくてはいけません。
義務1:外国人労働者と締結した雇用契約を確実に実行すること
報酬を適切に支払う等の基本的な項目を満たしていること
義務2:外国人への支援を適切に行うこと
支援の実施に関しては登録支援機関に委託することが認められている
義務3:出入国在留管理庁に各種届出を行うこと
具体的には特定技能雇用契約を変更・終了した場合の届出
以上3つの義務を果たさないと外国人を受け入れられなくなったり、出入国在留管理庁から指導や改善命令等を受ける恐れがあるので注意しましょう。
参考:特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 法務省
登録支援機関
登録支援機関とは特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人の支援計画の策定および実施を行う機関のこと。外国人を雇用したい企業に代わって、外国人を受け入れるための計画(※)を策定したり、計画に基づいて支援の活動(日本語教育や生活ガイダンスなど)を行います。登録支援機関について詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
特定技能を持つ外国人労働者は、人材不足の業種によって重宝される人材です。ただし特定技能の在留資格を取得するには、日本語や技能に関して一定以上の水準を持っている必要があります。また、受け入れる企業の側にも、満たすべき条件や義務が設定されています。特定技能採用は特定技能特化型のプラットフォーム[Linkus]がお手伝いいたします。また、自社支援・内製化については[特定技能アドバイザー]にご相談ください。