
国内で急速に増え続ける介護需要に応える手段のひとつとして「外国人材の活用」が注目を集めています。日本国内だけで対応しきれない人材需要に対して、海外の優秀な人材を雇用し介護事業を担ってもらう企業が増えている昨今。
外国人材が介護職に就くための在留資格は複数ありますが、この記事では特定技能[介護]について詳しく解説しています。なお、特定技能外国人の採用や在留資格申請のご不明点はLinkusが、自社支援に関しては特定技能アドバイザーがお応えします。ぜひご相談ください。


特定技能[介護]とは
特定技能とは日本国内において特に人材不足が深刻化している16業種において、外国人材の活用を促進するために2019年に新設された新しい在留資格です。介護業界においてもこの在留資格を活用して海外人材を登用することができます。
これは特定の分野において既に業務遂行に必要なレベルのスキルを有している人材が取得できる資格。技術研修や人材育成を目的とした在留資格とは異なり、人材不足に悩む現場において即戦力として活躍できる人材だけが、特定技能での在留資格を取得することができます。
特定技能の在留資格を得るためには、その職域におけるスキルと日本語能力に関して所定の試験に合格するか、それと同等の能力があると認められる必要があります。つまり、特定技能で滞在している人材については、その職域における技術と、業務を遂行できるレベルの日本語能力を有していることが証明されているということです。
特定技能に関する詳しい内容はこちらも参考にしてみてください。


介護業界の現状
日本国内の急速な高齢化の影響で介護を担う人材の需要も大きくなっているものの、十分に確保できているとは言い難い状況です。公益財団法人介護労働安定センターが令和5年度に行った調査では、事業所全体の従業員の過不足感は「大いに不足」「不足」「やや不足」を合計すると64.7%、より深刻な不足感を意味する「大いに不足」と「不足」の合計は34.0%という結果でした。
2025年前後は「団塊の世代」が後期高齢者となるタイミングであり、介護を必要とする人口は今後もさらに増え、比例して介護人材需要も増加傾向で進むと考えられます。加えて「同業他社との人材獲得競争が厳しい」「他産業に比べて、労働条件等が良くない」という声も上がっており、人材需要に十分な供給を得ることが難しいのが現状です。
参考:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について-公益財団法人介護労働安定センター
特定技能[介護]の資格取得の要件
特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、介護技能と日本語能力について、業務遂行に必要なレベルを有していることを証明する必要があります。具体的には、次のうちいずれかに該当する必要があります。詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

(1)介護技能と日本語能力それぞれについて所定の試験に合格
試験は日本国内だけでなく国外でも実施されているため、日本の在留資格を有していない人も自国で試験を受けられます。また、介護技能の試験は現地語で受験することも可能です。日本語能力試験は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験のN4以上に合格する必要があります。
(2)介護福祉士養成施設を修了
日本国内の介護福祉士の養成施設にて所定の課程を修了することで、資格要件を満たすことができます。「介護福祉士の養成課程を修了している=現場の介護において必要な技能を有している」と判断されます。また「所定の課程を日本語で修了した=業務遂行に必要なレベルの日本語能力を有している」という証明にもなるという考え方です。
(3)EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了
EPA介護福祉士候補者とは、EPA(Economic Partnership Agreement)を結んでいる国の出身者が、日本国内で介護福祉士となるための教育を受けるための制度です。この制度を利用し所定の課程を修了→日本の介護福祉士を目指すことができます。所定の在留期間を満了したうえで、介護福祉士国家試験にて合格基準点の5割以上の得点をし、すべての科目で得点を挙げると、(2)と同様に介護の現場で必要な技能と日本語能力を有していると判断されます。
(4)技能実習[介護職種・介護作業]第2号を修了
技能実習とは外国人材が働きながら現場で必要な技能やスキルを身につけるための、職業訓練的な在留資格です。技能実習[介護職種・介護作業]の技能実習を修了しているということは、介護の現場において十分な実務経験があり、必要な技能・日本語能力を有しているということが証明されているとされます。
技能実習と特定技能の違いについて、詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。
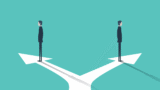
対象職種・任せられる業務
特定技能「介護」で従事することのできる業務は、「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入 浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お 知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。」としています。
介護施設などにおいて、直接的に利用者の介護に関わること、生活の補助をすることに加え、施設運営において必要な業務に広く携わることができます。その職域については、同等の業務に従事する日本人労働者と同様と考えることができます。
訪問介護について
2024年6月の有識者検討会において、訪問介護サービスへの特定技能外国人導入解禁の方針を決定しました。詳しい資料の内容は「第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会-厚生労働省」から確認できます。
これまで外国人で訪問介護として就労できるのは、[EPA介護福祉士(候補者は不可)][介護福祉士(在留資格:介護)][身分系在留資格保有者]などに限られていましたが、早ければ2025年度から特定技能外国人も訪問介護が可能となる見込みです。
雇用形態や報酬について
注意する必要があるのは、特定技能で働く外国人労働者の雇用形態です。特定技能で働く外国人労働者は、原則直接雇用である必要があります。一部派遣社員が認められている業種もありますが、[介護]においては事業所との直接雇用が必要です。また、当該外国人労働者に対する報酬は、同様の業務に従事する日本人労働者と同水準もしくはそれ以上である必要があります。
特定技能外国人の雇用契約書・条件書に関する詳しい内容はこちらも参考にしてみてください。
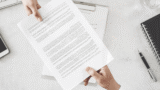
特定技能[介護]の申請書類
特定技能[介護]の在留資格で日本の介護現場で活躍するためには、所定の書類の準備が必要です。必要な書類には、外国人材が用意するものと、外国人労働者を雇用する施設が用意するものがあります。
外国人本人の有する資格や経歴、施設の種別や特定技能外国人の受け入れ歴などの条件によって、必要な書類の内容や対象期間が異なる場合もあります。必要な書類がどれに当たるのか、確認して書類の準備にあたってください。
- 提出書類一覧表
- 返信用封筒
- 証明写真
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 報酬に関する説明書
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書
- 健康診断個人票
- 特定技能外国人支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
- 介護技能を証明する書類…介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し、介護福祉士国家試験結果通知書の写し、介護技能実習評価試験の合格証明書の写しなど
- 日本語能力を証明する書類…日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写しあるいは日本語基礎テストの合格証明書の写し
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 関係する役員の住民票の写し
- 役員に関する誓約書
- 次のいずれかの書類…(初めての受け入れの場合)労働保険料等納付証明書、(受け入れ中の場合で労働保険事務組合に事務委託していない場合)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写しと領収書の写し、(受け入れ中の場合で労働保険事務組合に事務委託している場合)直近2年分の労働保険料納入通知書の写しと領収書の写し
- 社会保険料納入状況回答票あるいは健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
- 税務署発行の納税証明書
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書
- 公的義務履行に関する説明書
- 介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
- 協議会の構成員であることの証明書
Linkusならこれらの書類が、プロフィール情報の登録のみで自動生成できます。ぜひご相談ください。
特定所属機関(受入れ企業)の注意点
特定技能[介護]で外国人を雇用する際、受入れ企業側にも満たすべき要件があります。例えば、当該の外国人労働者が不自由なく業務に従事することができるよう、『特定技能外国人支援計画』を作成すること、計画に基づいて支援を実施することなどです。また、特定技能で滞在する外国人材を活用する事業所は、公的機関等の行う『分野別特定技能協議会』に参加する必要があります。
介護人材の不足の度合いは、その事業所の立地などによって大きく異なります。そのため、特定技能[介護]で働く外国人材を受け入れる人数上限は、事業所ごとに個別に設定されています。条件に違反することがないよう、自らの事業所の要件について理解し、遵守してください。
特定技能所属機関に関してはこちらの記事も参考にしてみてください。

まとめ
少子高齢化の進む日本国内では、今後ますます重要となっていく介護事業。必要な人材を確保し、できるだけ安定した運営を目指していくために、外国人材を採用する事業所が増えています。特定技能[介護]の内容を正しく理解し、自らの事業所の現状とニーズに合わせ、適切な形で活用していくためにも、ぜひLinkusにご相談ください。自社支援に関してのご不明点やご相談は特定技能アドバイザーがお応えします。ぜひご相談ください。


